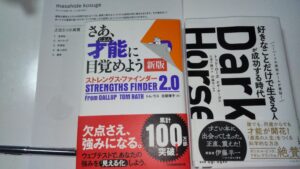昨日、本日に読んだ本です。私はだいたい平日は1冊、休みに2冊読みます。ほとんどは心理学、脳科学などの科学的に証明されたものです。今回はかなり良いものが当たりました。
右の本、ダークホースは好きなことをするだけで成功する時代でどう考えどう生きていくかという内容でハーバード大の研究です。私は起業してもうすぐ6年ですが、好きなことと得意なことしかしてません。起業時に立てた仮説はほぼ当たっていますが、この本はその裏付けとなりました。非常に心強い確信を持てました。
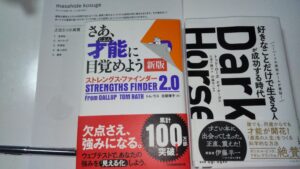 DSC_0482
DSC_0482
もう1つのストレングスファインダー2.0は「強みの心理学の父」ドナルド・クリフトンが作ったものが進化したアセスメントの内容です。これ、本当に良くできてます。活発性、ポジティブ、学習欲、最上思考、着想と私の資質をズバリ言い当てられました。私は得意なことだけやり苦手なことはしないと決めていますが、この本は自分自身の得意なことが何かを今まで以上に明確化してくれました。1,800円+税でこのテストができるのは格安と思います。
運の良さも統計的に証明されています。リチャード・ワイズマンというイギリスの学者が統計で導きだした「運のいい人の法則」というものがあります。この法則について5回シリーズで動画を出しましたので是非ともご覧ください。合わせて30分くらいです。これを見ていただいた上で「運のいい人の法則(リチャード・ワイズマン 角川文庫 文庫本で780円+税)をお求めになられるといいと思います。
これらの本と巡り会えた私は本当に運がいいと思います。本日は朝から10時30分までに4日分の仕事も入りました。「私は運がいい」といい続けると本当に運が良くなるのは科学的に証明させています。
その1
その2
その3
その4
その5
2021年11月のサミット人材開発の動画配信は「前向きに生きるための月間」を題してお送りします。今回は全9話の第9話、不幸を幸運に変えるリチャードワイズマンの「運のいい人の法則(角川文庫」のお話その4をお送りします。
運が良くなるには統計的にどうすれば良いかが分かっています。今回の動画は9分ほどと長めですがぜひご覧ください。。
一昨年に登壇した某市役所のクレーム対応研修ですが、昨年は価格が安いというだけの理由で他社に取られてしまいましたが私の研修と比べて内容が薄く効果がないという理由で、やはり小菅講師でないとと今年はご依頼をいただきました。大変光栄なことで嬉しく思っております。
研修のテキストの準備のため、その市役所が新しく作成されたマニュアルを見たら私の研修に準拠した内容でした。当然のことだと思いました。
なぜなら、私の師匠である柴田純男先生が苦情対応の国際標準規格ISO10002の意見書発行数トップクラスでこの分野の研修の国内第一人者でいらっしゃるので当然なことなんだと思ったわけです。柴田先生のノウハウは国内で標準化していくべきものです。もっともっと世の中に広めていくべき考えだと強く思っております。
心理学やカウンセリングに基づいた傾聴法はそれらを深く学んだ人間にしかできません。マナーの延長線とは異なるものです。柴田先生は食品のクレームの現場での実戦の中でご経験を積まれる中で独自に心理学を学び、大学教授や弁護士仲間などと日本説得交渉学会という学会を立ち上げ70歳を超えた今でも副会長の立場で熱心に学ばれています。私もその学会に参加させていただいております。
私の場合は国立の教育大学の教員養成課程で教育系のカウンセリング・教材作成・プレゼンテーションを学んだことをベースに25年を超える営業・クレーム対応の経験(いずれも現役です)の中での経験と今も続けている学びを融合させています。その上で柴田先生のノウハウを唯一人継承し、年間数百例のクレーム事例の分析、また柴田先生のノウハウの体系化など取り組んでいます。
また、実際に研修講師はクレーム対応をしたことがあるということは当たり前のことと思われますが、実はクレーム対応を一度もしたことがないクレーム対応研修の講師を知っています。そのような方が行う研修に何の意味があるのでしょうか。張りぼてとしか言いようがありません。柴田先生は食品の世界で、私は自動車、介護会社のエリアマネージャー、不動産業界でもう味わいたくないレベルのヘビー級のクレームを数多く体験しています。ガラス製大きく重い灰皿を眉尻にぶつけられて4時間血を流しながら正座させられ罵声を浴びたことがあります。その時の傷は今でも残っています。こんな経験があるからこそ深く、納得性・実益性が高い研修が出来ます。
これからも不当な要求には断じて応じないマインドを持つこと、理不尽なモンスタークレーマーやカスタマーハラスメントを世の中から撲滅していくため、柴田先生のお考えを少しでも多くのクレームに苦しむ方々に広めていきたいと思います。
2021年11月のサミット人材開発の動画配信は「前向きに生きるための月間」を題して全9話をお送りしております。今回はその8話。リチャードワイズマンの「運のいい人の法則(角川文庫」のお話、「運がいい人の法則」その3 運がいい人は幸運を期待するをお送りします。
目標を設定し、それを達成すると喜びの脳内ホルモンが分泌され、褒めてあげるとさらに脳内ホルモンが出るということが分かっています。喜び脳内ホルモンは脳にとって快感です。脳内麻薬とも言われ、一番快楽性の強いものは痛み止めのモルヒネの6倍ほどの鎮静効果があるそうです。なので脳は「もっと自分を気持ちよくさせろ」と指令を出します。これを繰り返していくことで脳は成長します。
部下や子どもへの指導でこのやり方を使わない手はありません。少し頑張れば到達する目標を明確に設定して、達成させ褒めてあげるを繰り返せば部下や子どもの脳、つまり能力は開発できます。
私には小学5年生の娘がおりますが、小学校に入った時から毎日欠かさず小さな目標設定、低学年の頃は明るいあいさつ、1日に10回授業中に手を上げるといったレベルで、現在ですと塾の宿題、学校の宿題をどこまでやりきるといった感じです。娘はまじめな性格なので毎日これを欠かさずにやっています。
これを繰り返していった結果、娘の脳は毎日喜んでいるようで自然とより大きな目標を掲げていくことにつながりました。1年生の時に中学受験して三重県で一番の進学校に入りたいと言い出しました。じゃあ4年生から塾に行かせればいいかと思っていたところ、2年生の時点で自分から塾に行きたいと言い出しました。3年生になったら某大学(日本の私学のトップ大学)に行きたいと言いました。こうしていくことで勉強を自らが進んでする習慣のベースを作りました。
国語と算数は学校・塾・家庭での学習で身に付きますが、理科と社会はそれだけでは厳しいです。理科に興味を持たせるには学研の図鑑と実験が有益でした。1年生~3年生の時には図鑑を毎月欲しいものを与えました。また、ホウ酸、カルシウム、ナトリウムなどの炎色反応の実験を自宅でしたことは娘の興味を理科に引き付けることができたようです。
社会は実体験が大事です。娘は10歳時点で既に25都府県に行っているので地理の授業を受けると「ここ、行ったことがある」となり、そこから興味を持つようになりました。また、国宝5天守のうち松江城以外は見ていることは歴史と地理の両面において意義がありました。昨日は家族3人で京都で紅葉を満喫してきました。京都五山の東福寺と大徳寺、小倉百人一首が藤原定家によって選定された二尊院、学問の神様菅原道真公が祭られている北野天満宮、日本のダヴィンチ本阿弥光悦の光悦寺、豊臣秀吉の菩提を北政所ねねが弔った高台寺などを回りました。娘の記憶に残ることでしょう。また歴史は小学館の学習マンガ日本の歴史が有益です。高校で学力が底辺にいた「ビリギャル」が慶應義塾大学に受かった理由の1つがこれです。
このような感じで私は娘に勉強をする習慣を身に着けさせました。私は今までに一度も娘に「勉強しろ」といったことは有りません。
2021年11月のサミット人材開発の動画配信は前向きに生きるための月間と題して全9話をお送りしています。本日はその第7話です。「運がいい人の法則」2 虫の知らせを聞き逃さないをお送りします。
最近、BIG BOSS新庄剛志さんにはまっています。実は私、新庄選手の親友の親友なんです。小学生の時からの付き合いで今も良くゴルフやご飯に行く広沢好輝くんは元プロ野球選手で、阪神タイガース時代に新庄さんと意気投合し、新庄さんがメジャーに行った時は練習パートナーとして帯同していたという経歴を持っています。
親友の親友昨年の現役復帰に向けての行動、そして今回の監督就任。大変刺激を受けてます。
企業の体質というものは本当に変わらないですね。かつて2013年度はブラック企業大賞にも選ばれてましたワタミ。またやらかしました。
昔は365日24時間死ぬまで働けが社訓、成績を出せない社員にビルの8階か9階での会議中「今すぐここから飛び降りろ」、2008年に新卒社員の過労自殺、その後7年半も謝罪せず。
2013年に渡邉会長(当時)が参議院選挙で当選し、議員をしていた6年は労働組合が結成されるなど当時の社長を中心にホワイト化していきましたが、渡邉氏の参議院の任期が終わり議員を辞め、2019年に渡邉氏が社長に復帰すると2020年9月に長時間労働と残業代の未払いで厚生労働省より是正勧告を受け、昨日執行役員による「45時間以上残業させてもいい」発言が本日発売の週刊文春にリークされました。
この動画がその内容です。
https://www.youtube.com/watch?v=pmsaaB-UYgI
企業の体質というものを変えていくのは難しいものです。不祥事を起こす企業は大体似たような曲線をたどります。
事例1 三菱自動車
1990年代はトヨタ・日産に次ぐ業界3位の車メーカー
2000年 大量のリコール隠しが発覚
2002年 大型トラックのタイヤ脱落による横浜での親子3人死傷事件
2003年 2000年の時以上の大量のリコール隠し発覚
その後、シェアは激減し冬の時代へ。徐々に盛り返すも
2016年 燃費データ改ざんが発覚
自社で存続が不可能となりルノー日産グループに吸収される
2017年以降、毎年4,000億レベルの赤字
現在存続の危機
事例2 東京女子医大
2000年の時点で創立100年の名門校
2001年 カルテ改ざん事件
2002年 特定機能病院承認取り消し
2007年 特定機能病院再承認
2015年 子どもに使用してはいけない麻酔薬を常時使用が発覚
再度特定機能病院承認取り消し
2017年度以降、毎年30~50億円の赤字
2020年 看護師の大量退職
2021年 医師の大量退職
現在存続の危機 他の大学が買い取る話などがニュースで出ている。
事例3 日本相撲協会
1990代は若貴が大ブーム
2003年 貴乃花引退 その後相撲人気は低下
2008年 時津風部屋リンチ殺人事件
2010年 野球とばく事件
2011年 八百長事件 この時協会は存続の危機に追い込まれた
その後、モンゴル勢の活躍
2017年 17年ぶりの日本人横綱稀勢の里昇進
2017年 横綱日馬富士による貴ノ岩への暴行事件
年末、暴行事件を受けコンプライアンス研修を実施
その中での八角理事長(元横綱北勝海)の発言
「何気ないちょっとした気持ちでやった暴力が、
ここまで組織を揺るがすような羽目になってしまうと。
本人たち個人個人の自覚を持って行動するようにと促しました」
この発言に世間からは本当に反省しているのかと反発を受けた。
2018年 貴ノ岩による付き人暴行事件
2020年 中川部屋暴力事件
親方や大関がコロナ禍の中の飲食店等への不要な外出などで処分等不祥事は絶えない。
この先、ワタミがホワイト化できるかどうかが注目です。
2021年11月のサミット人材開発の動画シリーズは前向きに生きるための月間全9話です。本日は第6話の「運がいい人の法則1 チャンスは最大限に広げる」をお送りします。リチャードワイズマンと言うイギリスの学者が明らかにした法則です。
運がいいか悪いかは統計で分析されています。また、私は運がいい人間ですがワイズマンの法則に大いに当てはまっています。確実にお役立ちできる内容ですので是非ご覧ください。
難苦情の中で病的なクレーマーへの対応というものがあります。今回はその中で誇大妄想型のクレーマーについてお話をして参ります。
昔、賃貸不動産物件の家賃保証会社の家主や管理会社向けの営業をしていましたが、家賃滞納の際の督促の現場を見るために1月ほど督促部隊に付いて勉強をしていた時の話です。家賃の督促に実際に行った時に話がまったく家賃と違うところに飛んで、
「私はねえ、旧皇族の北白川宮家の出身なの。時代が時代ならあなたたちなんて私の顔も見れないのよ。だから家の出が違うから・・・」
くどくど話は続いたところ、督促の担当者は「うんうん」と話を聞いていましたが、話が途切れたところで一言。
「で、家賃は?」
この一言で家賃滞納者はピキーン!!と固まりました。そして15秒くらいしたらハッとした顔で我に返ったと思ったら今度は
「S鉄道のT社長知ってるわね。ほんとは私はTから50億もらう予定だったの。」
典型的な誇大妄想型のクレーマーでした。わかりやすいくらいに。このように大きな話をするのがこのタイプのクレーマーだと覚えておきましょう。傾向としては自分の存在は大きいものと認めさせたく、心理的に寄り添ってくれる相手を求めるということです。そのため、個人が名指し指名されることを避けていきたいところです。
私がいた賃貸保証会社では督促チームは3人1チームでした。人が変わり変わりすることで名指し指名されず心理的に寄り添ってくるのをかわすということができます。クレーム対応を一人で背負い込んでしまうのは禁物です。名指し指名でターゲットにされてしまうと長時間の拘束につながりやすいです。
まず一時対応者が1時間対応をしてらちがあかなかったら、二次対応者が対応しますが、その時にわざと一時対応者と全く同じ説明をします。そして30分話をしたら三時対応者に変わり、これも全く同じことを説明するというやり方があります。一人で対応すると怒りはその一人に集中しますが3人で対応することで怒りは分散化され、取り付く島が無く誰に話をすればいいのかが分からなくなるといった効果が出ます。また誰に言っても話になりませんのであきらめるという方向に行きやすくなります。
不当な要求や無理な難クレーム、病的クレーマーなどの相手をしている時間はもはやありません。基本的にはクレームはたらい回ししてはいけませんが、「あえて」たらい回す場合もあると覚えておくと良いでしょう。
実際に起きているクレームの事例に対して、研修でこのように対応した方が良いという指導をしますが、かなりえげつない内容を良く聞きます。本日は1つお話を紹介します。研修の事前に事例をいただいておりまして、その話を研修に取り入れ話しましたら、その当事者が研修にご参加されていました。その方は小学校の先生でした。多少脚色を加えますがこのような話でした。
Aちゃんがクラスの女子数名から無視されるなどいじめがあるということで、A母から学校に連絡が入りました。それを聞いてまずは状況を確認するため該当する児童から話を聞いて、実際に無視をするといったいじめがあったことが明らかになりました。そのため「個別に状況を聞き取った上で該当する児童全員で話し合い、仲良くするにはどうすれば一番いいのかを決めていく」ということにしました。
それをA母に伝えたところ、
「それではダメだ。甘い。それでうちの娘へのいじめが収まるとは思えない。親と子供全員で話し合わなければこの問題は絶対に解決しない」とのことでした。
この話を上司である学年主任に相談すると
「親同士の話合いは避けるべき。とにかく良く話を聞いて納得してもらうことだ」と指導をしてもらったのでそのように対応したのですが、何度話をA母の聞いても意見を曲げることは無く1か月の間、毎日2時間の電話をしてきました。それに対して学年主任は「とにかく聞け」の一点張りで板挟みとなり、大変つらい思いをしました。最終的には見かねたA父が電話を止めさせてくれましたが、5年前の話ですが今でも思い出すと吐き気がします。
相当悪質なケースです。親を含めての話し合いは絶対に避けるべきです。なぜならば例えば私のようなクレーム対応の技術をもった説得・交渉の専門家が親の一人とすればA母側の意見など叩き潰すことは容易ですし、下手をすればAちゃんが吊し上げになる可能性すらあります。(私はそんなことはしませんが)大変危険なことです。なので「学年主任に相談したところ、以前そのようなことがあったので避けるべきで、最悪Aちゃんが孤立しかねないリスクがある」と指導を受けたという話をするとよいでしょう。
また、この学年主任は間違いなく昔の「とにかく聴け」というクレーム対応研修を受けていると考えられます。この指導が大変まずいです。こんなカビの生えたやり方をするから教員の皆様が疲弊してしまうのです。自治体の窓口や一般企業の場合でしたら「出入り禁止」といった切り離し対応ができますが、学校の場合そうはいけませんので、この場合は「この件に関してはもう一切話をしません」と人間関係を切るのではなく1つの話に関して切り離すことが大事です。
2021年のクレーム対応のスタンダードは2時間が限界です。それ以上の話はぶった切ってしまいましょう。また、このケースは威力業務妨害罪で訴えることは事実難しいですが、ここまで執拗で5年経っても忘れられないような状況になっている場合「傷害罪」で訴えることが可能です。私の不当要求対応研修を受講した現役の刑事の方がおっしゃっていました。