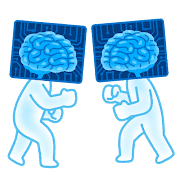
ここ3年ほどで凄まじいスピードで進化するAI。実際に仕事で活用できる場面も増えてきています。
例えば研修カリキュラムを作らせたり、カスハラ対応のガイドラインの文章を作らせたり、提案書やチラシの文章を簡潔なものにしたりといったところで実用化してます。
新しくAIの会社2社と組むことにしました。A社は研修のテキストの内容をAIに読み込ませることで研修内容の確認テストを生成してくれることと、カスタマーハラスメントが起きた時のデータを読み込ませることで対応事例を作ることができます。もう1社のB社は営業やクレーム対応、部下指導のロールプレイングの相手としてAIを活用することです。A社ではテレアポの受付突破までは既に対応できるとのことで、本当に進化して実用化できるようになってきたことを実感します。
ただ、私の場合ですが仕事を奪われると言うことはまだまだないと感じています。今の段階はやれるところまで仕事を進めてくれる「部下」が増えたといった感覚です。私がAIに使われるといったことはまだまだ先だと思っています。
また。講師の仕事は奪われないでしょう。今年は東は茨城から西は長崎まで日本の都道府県の半分以上に参りました。やはりリアルで話を聞きたいという需要があるのですが、AIには物理的な体がありません。研修では講師そのものの存在が求められます。8年くらい前に立体映像が見れるテレビが全く売れませんでしたが、よほど生身感覚のものが発明されない限り、講師の存在が無くなると言うことは考えにくく、まだ数十年は先を越されることは想像できませんね。
また、これからは多くのホワイトカラーの仕事をしている人が製造業、サービス業、介護に流れていくことが予想されますがこの3分野の研修は得意なのでむしろ仕事が増えることが予想されます。
新しいテクノロジーが出てきた時はビジネスチャンスです。代わらない世の中であるときは既得権者が優位ですが、世の中のルールが変わる時は新参者が取って代わることができます。実際に5年前のコロナ禍の際は研修も営業もオンラインに切り替わることを幸いすぐに見抜きました。すぐに友人が主宰するZOOM講師養成講座を受講し、高品質な機材を買い求め、ボイストレーナーについてマイクを通しても良く通る声にしてもらい、10回ほど友人を集めてオンラインセミナーの練習をしてオンライン研修のしかたをいち早く完成しました。我々講師業界は60代以上のパソコン等の取り扱いを苦手とする講師が多く、その方々が「ZOOMがつながらない」と言っている間に、提携先の研修会社に「いち早くオンラインでも効果の出る研修が実施できるようになりました。」と売り込み、多くのオンラインの研修を受注しました。また、コロナ禍以降お打合せは現在もほぼオンラインなので、全国各地から仕事が取れるようになりました。
ピンチはチャンスです。AIに使われたり仕事を奪われるのではなく、いかにAIを自分の部下、手足として活用するかを考えていかなければなりません。
人材採用とマネジメントのホームページ、あるバイHRの
「【2025年版】企業向け研修サービス|社員の成長を加速させる注目プログラム」に
弊社の記事が掲載されました。ぜひご覧ください。
【2025年版】企業向け研修サービス|社員の成長を加速させる注目プログラム | あるバイHR
今日は商談のその場で1件受注。その後、メールで1件ご依頼がありました。
前者は公的な人権団体様で、「話した内容に対してここまで完璧な提案をいただいたことに感動しました。」と、大変嬉しいお言葉をいただきました。もう1件はこれで10年連続のご依頼です。
「初めまして」の最初の商談は必ず会社のロゴマークと同じ色、濃紺のスーツとオレンジイエローのネクタイで伺います。濃紺は研修会社として最も必要な誠実さと安心感を、オレンジイエローは私の勢いと躍動感を示しています。また、必ず相手に合わせた雑談を入念に準備します。先週の商談では、東京都港区芝の会社様でしたが、以前その近くに住んでいて、そのあたりでプロポーズをした思い出の街なんです。といった話ですぐ打ち解けました。
ちょっと前には百貨店がらみの仕事の際は、「私、実は百貨店の運営会社の息子なんです。」といったトークが受けました。忘れていましたが、かつて伊勢にあった三交百貨店の管理会社の社長をしていたことを父がしていたのを思い出してのトークです。
ある美容外科クリニックの時には「御社はものすごく大変なクレームが多いと思います。日々皆様、大変な思いをされているかと考えます。我々の業界では食品会社の○○社、高級マンションの○○社、熱狂的なファンが多い○○社、そして御社が日本4大クレームが大変な会社と言われています。実は他の3社は私が担当していますが、本当に大変なんだと思いますので、是非御社に貢献ができればと思い、今回は伺いました。」といった話を準備して、後2社の話を聞く段階だったのが、その場で内定的な言葉をいただき、受注に至りました。
私の仕事は決裁権者や人事教育担当者相手です。企業は人事には優秀な人材を置きますので、清潔感と確立した自分らしいスタイルで第一印象を良くして、すぐに打ち解けて「この人、凄そう」と一発で感じていただき、仕事をいただくよう、このような準備をして臨んでいます。営業におけるアプローチは沈黙のクロージングとも言います。最初の何分かで勝負はつくものです。そのためには見た目の印象、感じの良さ、親しみやすさを演出すること、これ大事です。
よく、小菅さんの得意な業界は?と聞かれます。こういった時はこのようにこたえています。
「基本的に不得手な業界はありませんが、ご依頼が多いのは建築・不動産業、物流業、病院・介護業、製造業、自治体です。」
それぞれ理由がありますが、建築・不動産については元々不動産会社の息子であることが大きいです。常に土地に関する裁判や争いに子どもの頃から接していましたし、高校生の時(16歳)に父が不在時にはスーツを着てネクタイを締めて土地の境界争いに行ったこともあります。父は勤めていた会社を退職後、三重県伊勢市のランドマークだった百貨店の管理会社の社長をしていた時、最悪な事態になれば私の実家が14億円の負債を追わなければいけないといった非常事態に11年関わりました。新卒時は三菱ふそうでトラックの営業をしていました。トラックは現場で使うものなのでその現場に合わせてカスタマイズをします。現場の状況を分かっていなければトラックを作れませんので、自然と建築にの知識が付いていきました。また、不動産ファンドと賃貸物件の保証会社に在籍したこともあります。建築の最大手の会社M社様や、マンションのブランドが有名なD社様他多数の実績があります。現在、建築部門のある会社の人事顧問をしております。
物流についても三菱ふそうでの経験は大いに役立っています。
先日、1週間で建築会社2社、産業廃棄物業者向けのセミナー、自動車の輸送の会社と立て続けに4件の新規研修のご依頼がありました。これはふそうにいたおかげで取れた案件です。
病院・介護については30代の頃に当時最大手の介護会社であったコムスンに在籍して、京都府と滋賀県のエリアマネージャーになり、認知症のグループホームの営業で病院やケアマネージャー相手の営業を行い、そのホームを満室にしたら20か所近いホームの運営をした経験が生かせています。
製造業は、父が製造会社にいたので子どもの頃から工場に出入りしていたこと、大学生になった時に父の実家である小菅家に養子入りしましたが、そこが工場をやっていて手伝いをしていたこと、大学で中学の技術や高校の工業・農業等の教員免許を取る学科にいたので、旋盤、ボール盤などを扱い、溶接の経験もあることといった経緯で一通り製造業の皆様がやっていることを経験していることが大きいです。
自治体は仕事を受けていくうちに経験値を付け、2,000件ほどの事例を蓄積した結果、完成度が非常に高い自治体向けの研修が出来上がっていきました。
さらに最近では小売り・スーパー・商業施設、飲食店などのカスハラが多い業種からも良く声がかかります。三重県のスーパーチェーン、飲食チェーンでは研修とガイドライン作成を行いましたし、サッカーのJ2Vファーレン長崎の本拠地である新設された長崎スタジアムシティの研修も7月に担当しました。
カスハラから大事な従業員を守ることを企業に義務付ける法改正が目の前に迫っています。そのために研修やガイドラインの作成が必須となってまいります。
「法律に基づいてグ遺体的な言い回し、対応、コミュニケーション、の取り方と110番通報基準を具体的に学ぶ研修と、明確なルールであるガイドライン作り」
これこそがサミット人材開発株式会社の真骨頂です。弁護士方々の法律論の研修は必要ですが、コミュニケーションの取り方は学べません。マナーやコミュニケーションの先生はその内容を教えることはできますが、法律をご存じではありません。小さい頃から裁判や争いごとを見てきており、職業柄色んなもめごとの相談や支援をしてきた中で法律の実務や警察の動かし方も覚えました。また、受講生に法律の専門家や警察の方が毎年参加される中、議論ができたことも大きかったです。来るべき法改正に向け、ぜひお気軽に弊社にお問い合わせをくださいませ。

この3年ほどでカスタマーハラスメント対応のガイドラインを10社くらいで作ったり、監修しました。ガイドラインとマニュアルの違いはCANかMUSTです。ガイドラインは「こうしてもいいよ」で、マニュアルは「こうしなさい」です。クレーム対応には決まったマニュアルよりも、「このような状況になればこうしてもいいよ」としておいた方が働き手としては気が楽になるわけです。
以前監修したある化粧品会社では、5~6年前から男性が化粧をするようになったのでデパート・百貨店・ドラッグストアなどのお店に男性が来客する機会が増え、その対応に困っていました。対応するのは女性の美容の専門家。美容のプロなので容姿に大変気を払っており、大変接遇のレベルが高いので、若い男性には「この子、俺に気があるんじゃないか」と勘違いをさせてしまうことがあり、「どのあたりで飲んでいるの?」「どこに住んでいるの?」とプライベートに踏み込まれたり、1日のうちに何度も来店したりといったストーカーまがいなことをされたり、と言うような感じでどのように対応していいのかがわからず、大変困っておられました。そこで「断ることだったらこの人だ!」とありがたいことに私に白羽の矢が立ち、ガイドラインの監修をすることになりました。基本的な考えとしては「毅然と断るべきことは断る」「美容以外の話はしない」といったコンセプトで作成しました。
例えば
・プライベートなことを聞かれた場合は、「私は美容のプロですのでプライベートな事等美容以外の話はしません」と断る
・男性の化粧にはそんなに時間はかからないので来店は1日1回まで、1回15分で帰ってもらう
・フルネームの名札を付けているとSNSで特定されるリスク、また馴れ馴れしく下の名前を呼ばれるので名字だけにする
・転勤があった場合、異動先は教えない
・おみやげは一切貰わない
といったルールを徹底的に作りました。完成後、現場の皆様には大変好評でした。「これで男性は全く怖くない」ということで安心いただける結果となりました。
私のクレーム・カスハラ対応の研修やガイドライン作りはこのように「働き手が前向きな気持ちで安心安全に働くことが出来ること」が目的です。少子化が進み、働き手の確保が難しい中、貴重な人財をクレームやカスハラで失ってしまうのは企業や組織にとって大きな痛手です。そのような事態を防いでいきたいとお思いでしたらお気軽に私にご相談ください。

3年ほどほぼブログをお休みしていたのですが、またボチボチやっていこうかなと思って再開しました。改めてよろしくお願いいたします。
企業の人事顧問をしているので若手社員と接する機会があります。また、若手の研修を担当することもあり、先日は自治体で新卒2年目の研修でちょうど100名の若手職員たちと接しました。このような機会も多くあります。
若手から良く聞く言葉が「コスパ タイパ」です。コストパフォーマンス(費用対効果)、タイムパフォーマンス(時間対効果)の略ですが、「ほんとにパフォーマンスなの?」と思うことが多々あります。
良くあるのが「それってやる意味あるんですか?意味のないことはコスパ・タイパ悪いんでやりたくありません。」といったセリフです。これに対してまず言いたいのが、「君は何が意味があって、何が意味がないのか判断できるだけの能力があるのか」ということです。意味があるかどうかなどやってみないと分かりません。そんな判断ができるほど賢い人など世の中にほんのわずかしかいません。君はその中に入っているのかと問いたくなります。
そんな言い方をするときつくなってしまうのでこんな話をします。
「30年前に私は新卒で三菱ふそうに入ってトラックを売っていた。主に販売先は建築会社や物流会社で、そういった会社がどのような事をしているか、現場を見てきた。建築や物流会社の昭和的な古い慣習なども見てきた。トラックは現場の仕事で使うものなので現場を良く知る必要がある。その中で、ごみを回収する車のパッカー車や、自動車を乗せる車載車なんかも売ったことがある。そんな経験が30年経ってからなぜかまとめて活かされた。先月(令和7年8月)で新規で4件研修のご依頼をいただいたんだけど、1つめは建築会社で、建築のことを良く分かっている講師がいいということで6社の研修会社の競合の中から選ばれた。2つめも建築会社で、建築会社の昭和的な古い慣習や起きてしまったパワハラについて話ができるといったことで選ばれた。3つめは自治体の仕事で産業廃棄物の業者向けのセミナーの話、4つめは車両の輸送の会社の研修の話で、パッカー車や車載車を理解している講師などどこを探してもまずいないので単独ご指名をいただいた。その時はこんな経験が何の役に立つのか分からなかったけど、今になって無茶苦茶役に立ったんだ。意味があるかどうかなんて、誰も分からないんだよ。私は30年経ってようやく気付いた。」
こんな実話、話してみると若手に結構響きました。それに付け加えて
「経験値や能力と言うのは成功体験とは比例しない。それらは失敗も含めてトライした回数に比例する。講師の仕事なんてまさにそうで、成功体験よりもどれだけ失敗してきたかを語れる講師の方がいい講師なんだよね。クレームに苦しみまくった話、部下からクーデターされた話、部下からのクレーム、不祥事を告発したら上司に隠蔽され左遷されたこと、仕事と親友と彼女を同時に失ったこと、最速一部上場記録を持っていた会社の不祥事による経営破綻を経験したこと、最速マザーズ上場記録を持っていた会社の隆盛と衰退(リーマンショックで倒産で職を失う。結婚披露宴を行った2か月後の話)、パワハラを受けての退職、コロナ禍の始まりで2か月仕事ゼロ・・・挙げればきりがないけど、こんな経験をしたからクレーム・カスハラ対応、ハラスメントと部下指導、コンプライアンスなんかを語れる訳。失敗体験こそ宝ものなんだよ。」
ここまで話すと本当の意味でのコスパ・タイパを理解させることが出来ます。
管理職の皆様は昔の成功話の自慢はやめましょう。若手が飲み会に来たがらないのは下らない自慢話を聞きたくないからです。今の若手には成長意欲はあります。失われた30年の中で不安な気持ちが強い傾向があるので、しっかりとスキルを身に着けてどこでも通用するようになりたい気持ちがあるからです。失敗することの大事さ、未来に向けての前向きな話をするならば、若手は喜んで一緒に飲みに行ってくれるようになります。
https://keysession.jp/media/cases-of-customer-harassment-at-city-hall-and-countermeasures/

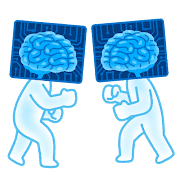
-pdf.jpg)
-pdf.jpg)


